 |
 |
「主に私の担当は本作りとか監督の選考とか、一般的なプロデューサーの仕事をスタートとしながら、どうやったら映画が興行として立ち上がるか、そのために経営の責任者のサポートを支えていく、という、いわゆる先頭部隊としてです。
現場と制作サイドの、いろんな問題が起きたときの対処です。」 |
 |
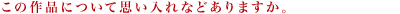 |
| 「最初『レディ・ジョーカー』っていうタイトルが、耳障りが良いなと思ったんですよ。しかし、原作を読むと僕がイメージしたよりも奥が深くて、すごく細かく書かれているんです。でも結論を出している本ではない。そこのタイトルに集約したという高村さんがすごいなと。やっぱり髙村さんはいつも、解決できないことにペンでメッセージを送っている、と。それを物井清三という渡さんが解決はしないんだけど、じっとしてないで一石投じた。作り手はみんなそこにたぶん面白さを感じたと思うんです。」 |
 |
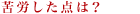 |
「人を動かすっていうことはお金が発生しますから、当然。本作りにしても人が参加するとお金がかかってきますし、それを長い期間やってますから、それが立ち上がらなかったら当然ペナルティが発生するわけですよね。それを、ずっとお金をきちっと払える体勢を作っていくことが一番大変でしたね。現場も不安がらせないように。
で、監督と約束したのは、「全体をやるという方向にみんなを向けてくれ」と。断念しないように、経営がここでストップといわれると、60人ぐらいの現場スタッフやそれに関わる2、30人、全部で100人近くの人たちの雇用がぽーんと飛んじゃうわけですから、そのへんがすごく不安だったですね。気がついたら終わっていたという感じで。」 |
 |
 |
| 「よかったというより、まだですね。俺のレディ・ジョーカーは終わってないんですよ。立ち上げて作って、なおかつ、興行を打って結果が出て批評が出て。要するに一般の人の評価と、業界の評価と。そういうのがある程度出ないと。企業人としてみればヒットしてくれればそれでよい、という話ですけども、作り手としては、多くの人のどういう評価があるか、と思うし。とにかく一生懸命、これから宣伝していかなきゃいけないし、がんばらなきゃいけない、と。」 |
 |
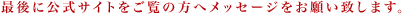 |
| 「まず「レディ・ジョーカー」ってなんだろうって考えてほしい。そうすると、また違った映画の見方ができると思います。」 |
 |
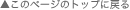 |
 |
 |
 |