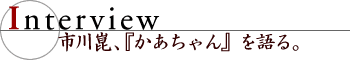---『かあちゃん』は市川監督にとって、長い間大切にされてこられた企画と聞いています。それは夫人の和田夏十さんが脚本を遺されていることからも窺い知れるのですが。
市川:『かあちゃん』は大好きな山本周五郎さんの下町モノのなかでも、僕も夏十さんも特に気に入っていた名作でした。最初に読んだときから「いつか、これを映画化したいね」と二人で話していました。57年頃、僕が大映で三島由紀夫さんの「金閣寺」の映画化(『炎上』)を進めていた時、住職さんからクレームがついて映画化が暗礁に乗り上げたことがあったんですが、ちょうどその時に、大映京都の撮影所長から「今度、新人監督をデビューさせるので、ついては市川さんと夏十さんで何かホン(脚本)を書いてほしい」と頼まれたんです。僕としては、将来のある新人監督にいい加減なホンを提供するわけにはいかない、かと言って「金閣寺」のことも気になってそれどころじゃない。そこで前からいろいろ考えていた「かあちゃん」を、あれだったらきっといいものになると思って「夏十さん、あれを書こうか」と引き出しを開けてしまったんです。結局、ほとんど夏十さんが書いて、いいホンがあがったのですが、その後、新人の作品だから、60分の中篇にしてくれとかの注文が出て、ホンを削ったりしなければならなかった。だから、脚本のクレジットも二人共通のペンネームの久里子亭にした筈です。でき上がった映画(『江戸は青空』)も見ましたが、悔いも残った。夏十さんとは、何年かたったら僕たちで心ゆくまで「かあちゃん」をやろうね、と言っていたんです。
---結局、実現せずに夏十さんも亡くなられて、ずっと時間がたってしまったと。
市川:僕のなかではずっとくすぶっていたのです。それで昨年、映像京都の善さん(西岡善信)と次の作品を話し合ってとき、そろそろどうだろうか、と思った。つまり『かあちゃん』は江戸幕府の政治が混沌として庶民の将来に展望がない時代の話でしょう。今の時代にちょっと似てるんじゃないか。それで竹山洋さんにホンを加筆してもらった。映画というのは、単純なヒューマンドラマではダメで、現代性にどこか通じていないとダメなのです。
---今回、クレジットで久しぶりに和田夏十さんのお名前に接して感慨がありました。
市川:クレジットされたのは『東京オリンピック』が最後だったですね。夏十さんは、そのあと僕が脚本で困っている時には、何かとアドバイスしてくれました。もともと、あれだけの名脚本が書ける人なんだけど、プロとしての意識はあまりなかった。ダンナが頼むからしょうがなく書いているんだ、と(笑)。ですからホンを書く時も応接間の机で書いたり台所で書いたり。あの人のやりたいことは、子供の育児や家事、そして少しエッセイを書きたいとか。これらも見事でしたね。作品によっては、ホンの内容でぶつかることもありましたよ。書くものは人間とか人生とかにかかわることですから、お互いの考えの違いが解ることがある。夫婦ゲンカではないですが、何となく、2、3日口をきかない(笑)。しかし白旗を先に揚げるのは僕のほうでした。