長谷部安春監督
──『女番長 野良猫ロック』に主演の和田アキ子について。
長谷部 とりあえず和田アキ子ものを、という企画でホリプロに外注するということでした。そこへ日活の若い女優をからめるというのが製作の主眼だったんです。和田さんもそういうような売り方だったし、日活の方も「不良少女」ものみたいなのはどうだ、ということでしたね。
──脚本の永原秀一さんは監督の起用ですか?
長谷部 そうですね。『女番長 野良猫ロック』の前の『野獣を消せ』で一緒にやってまして、「面白いもんやろうよ」と話はしてたんですよ。で。「野良猫ロック」の企画が来たときに、会社へ永原でやらせてくれ、と。
──では脚本はお二人で?
長谷部 そうでしたね。丁度「よど号事件」のあった頃でね、2カ月くらいかかりました。
──オプチカルについて。
長谷部 製作はホリプロといっても「ホリ企画」が主体で、そこは劇映画は初めてだけれどもCMは多くやってて、オプチカルが自由に使えるからなるべく使ってくれ、ということで。今のビデオなら雑作もないことでしょうが、当時のフィルムでは時間もお金もかかるから日活ではなかなかできなかったから喜んでやったんだけれども、上手くいった部分といかなかった部分がありますね。
──バイオレンスの衝動について。
長谷部 バイオレンスって、どうも後から言われ出したたんで……まぁ「アクション映画」が面白いとは思ってましたね。だから、男と女が抱き合うよりは、男と男が殴り合ってる方が面白いし、銃撃ち合ってる方が面白い(笑)。だから指向というより嗜好だろうと思うんですけどね。
──悪役をヤクザじゃなく右翼にしたのは?
長谷部 丁度「盾の会」が始まった頃じゃないですかね。僕も永原もそうですけど、ある種の意図を持ってやるというより、世の中の方が面白いということの結果だろうと思うんだけど。僕は意図的に映画を作るってことが好きじゃないんですね。だから、そういう設定でどう面白くなるか、ということだったんだろうと思います。永原も同じ考えでしたね。
──「野良猫ロック」シリーズでは今までの映画とは男女の立場が逆転してて、男の弱さが強調されていて、女の強さ、自由さ、タフさが出ているような気がします。
長谷部 それはやっぱり、テーマというか女の子ものというつもりで作ってますから。
──ラストシーンは「渡り鳥」ですね?
長谷部 そうですね。そういう感じってのは、なんとなく日活的なんじゃないですか?(笑)
──『~セックス・ハンター』ですが、元々は違う企画だったとか?
長谷部 そうですね。「夜の最前線」ってシリーズ、それだったんですね。いきさつはハッキリ覚えてないけど。
──出演した安岡力也さんについて。
長谷部 『あしたのジョー』のときに、マネージャーを通して僕に会いたいと。力也のことは東宝の『自動車泥棒』を観て知ってましたが、会ったらいきなり「力石は俺ですね?」って(笑)。彼は「力石は俺だ!」って頭から思い込んでいたんですね。いろいろ事情があってそれは出来ないんだ、いつか君とは必ず仕事したいからと話したら「この次ね!」って(笑)。次って言われてもアテがないから確約できないと言っても「イヤ、この次は俺絶対出ますから」って。脚本の大和屋竺にそんな話をして、会社にも安岡力也を使いたいからと言って脚本作りを始めたんです。
──敵役のバロンについて。
長谷部 1作目もそうだけど、悪役という風には考えてなくて、イイか悪いかより考え方が違う者のぶつかり合い、という方が強いんじゃないかな。
──バロンの大きなコンプレックスを持つ原因がきちんと描かれてますね。そこがドラマの中の対立構図になっています。
長谷部 そのアイデアも大和屋竺から出てきたのかな。
──監視塔のシーンについて。
長谷部 あれはセットで建てたんですよ。金網のフェンスもね。
──西部劇のようでしたね。あそこは西部劇で行こうと?
長谷部 そうでしたね。
──『野良猫ロック マシン・アニマル』について。
長谷部 これは会社、製作部や営業がタイトル決めてましたからね。『~セックス・ハンター』終わってすぐ脚本に入ったから、ずいぶん忙しかった。
──脚本は中西隆三さんですが?
長谷部 彼とは入社が同じ同窓でね。だから『皆殺しの拳銃』も彼だったし、彼は僕が監督になるより前に1本立してました。
──今回は『マシン・アニマル』というくらいで、バイクとジープ軍団のチェイスがありますけど、斬新だったのは、女の子たちがホンダのショップからミニバイクを連ねて来ますね。
長谷部 丁度ホンダダックスが売り出し中でね。1台じゃ画にならんから軍団なら面白いだろうと。でも大変でしたよ。重慶飯店の中を走るとかダルマ船の上を走るとか、仕掛けが大変でした。
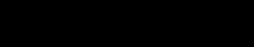 DVD-BOXのみの特典です。 DVD-BOXのみの特典です。
|

